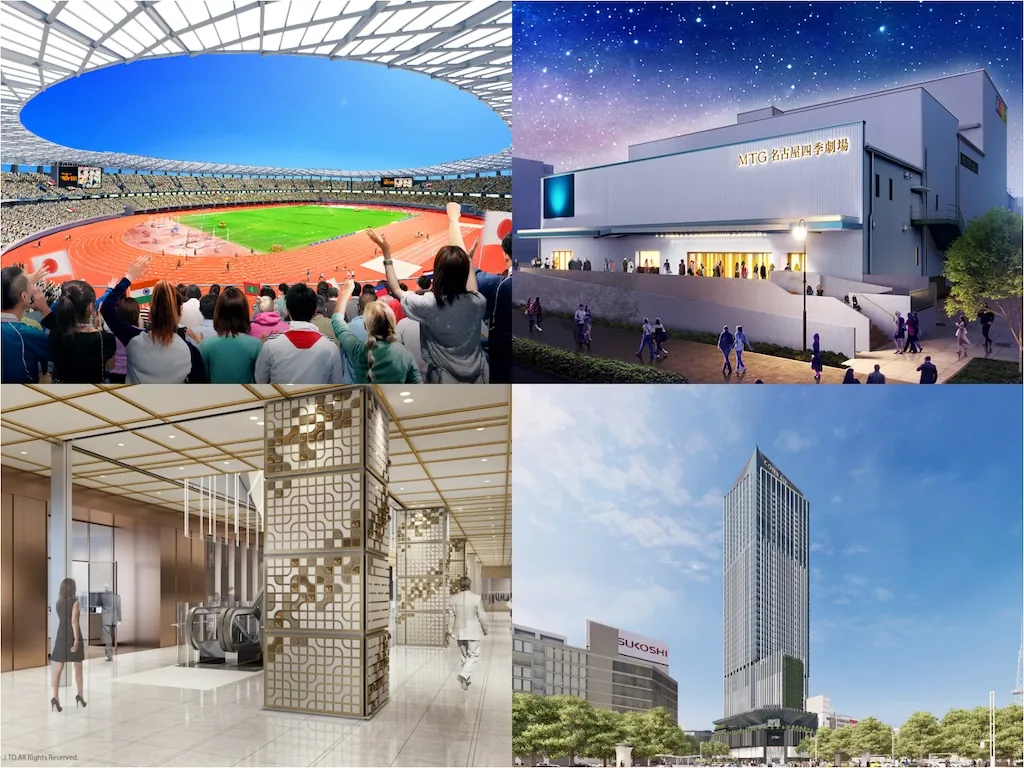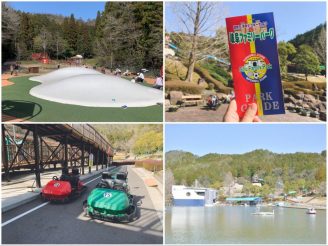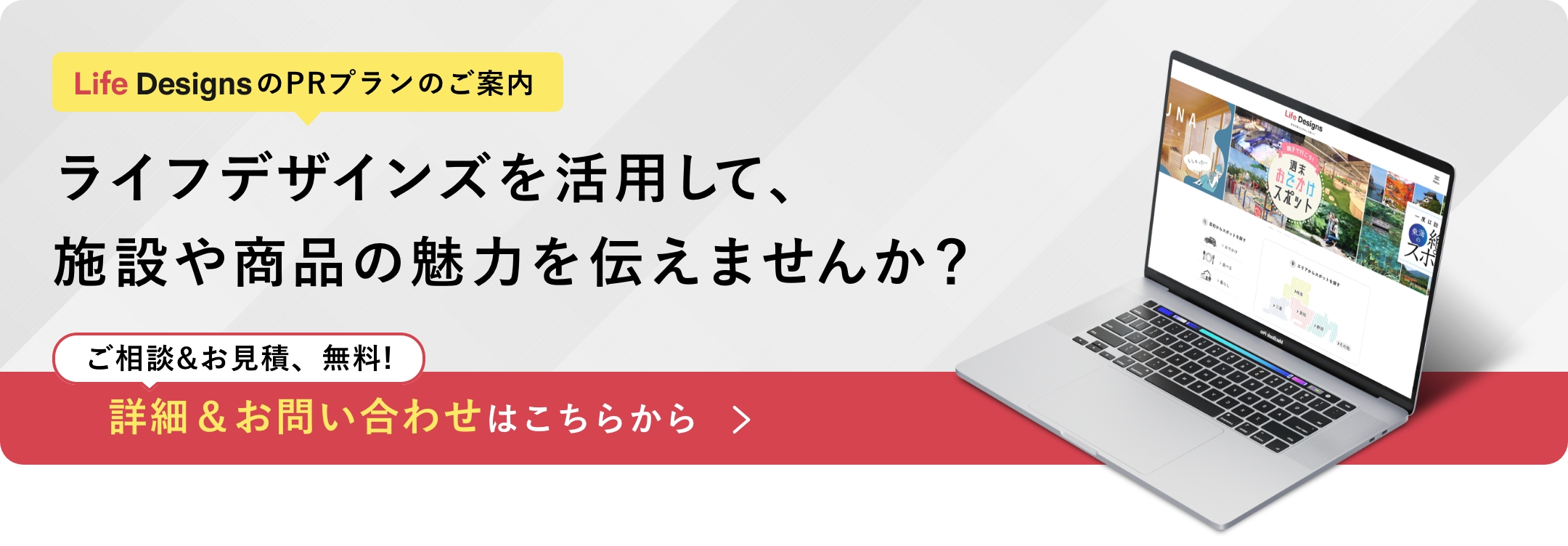作家・松浦寿輝さんの芥川賞受賞作『花腐し(はなくたし)』が実写映画化。監督を務めるのは、映画『Wの悲劇』や『ヴァイブレータ』などを手掛け、日本を代表する脚本家のひとりである荒井晴彦監督。
“ピンク映画界の斜陽”という原作にはない大胆なモチーフを脚本に取り入れ、ふたりの男とひとりの女が織り成す、切なくも純粋な愛の物語を描いた今作。現在と過去をモノクロとカラーの映像で表現、エンドロールの最後で彼らの“真実”に辿り着くかのような構成など、今作ならではの演出にも注目です。
荒井監督が演出と脚本に込めた想い、主人公・栩谷を演じた綾野さんが“役が生きる”ために意識し続けたこだわりなど、映画『花腐し』の世界をより深く楽しむための話をたっぷりインタビューしました。
■あらすじ■
斜陽の一途にあるピンク映画業界。栩谷は監督だが、もう5年も映画を撮れていない。梅雨のある日、栩谷は大家から、とあるアパートの住人への立ち退き交渉を頼まれる。その男・伊関は、かつてシナリオを書いていた。映画を夢見たふたりの男の人生は、ふたりが愛した女・祥子との奇縁によって交錯していく。
目次
カラーとモノクロで表現した
“思い出”に対する想い

– 大胆な脚色も見どころ。原作のなかで一番大切にしたことを教えてください。
荒井監督:「原作のラストシーン、“最後の一節”だけは外せないと思った。原作は栩谷と伊関が喋っているだけなんだよね。それで、どうやって映像化していこうかなと思って(笑)。だから、どうしても自分が外せないと思った最後のシーンと、「こんなに濡れて、あなた、傘の差し方知らないの?」と祥子と栩谷が会話をする雨のシーン。あと万葉集。このあたりを大きな骨格として残して、その骨格の真ん中をラストに向かってどうやって埋めていこうか考えながら進めました。原作をけっこう変えたと言われるけど、骨格は残したつもりです」

– 現在のシーンは「モノクロ」、過去のシーンは「カラー」というように、映像上の演出もかなり印象的でした。
荒井監督:「この演出は昔からやりたかったんだよね。現在をカラー、過去をモノクロやセピアで表現する映像はよく見かけるけど、個人的には“過去の方がずっと輝いていたんじゃないの?”っていう想いがずっとあってね」
綾野さん:「思い出や葛藤した記憶という過去が、現在を生きる栩谷と伊関の二人にとって“カラー”として残っているのはある種、残酷です。映画的演出として表現されているからこそ、現在のモノクロは、芝居で情報過多なサービスは必要ないと判断しました」

荒井監督:「青春時代に戻りたいかと言われると、微妙な部分もあるけれど、楽しかったなという想いはある。だから劇中で、大瀧 詠一さんの名曲「君は天然色」の、“想い出はモノクローム 色を点けてくれ”という一節を、金 昌勇役のマキタスポーツさんに歌ってもらってね。観ている人に説明していたりします。実はあのシーンで、本編には入っていないけど、綾野も歌ってるんだよね」
– え、そうなんですか!? それは「アドリブ」としてでしょうか?
綾野さん:「マキタスポーツさんにアドリブでギターを渡されて、“弾いてみる?”と。思い切って弾きました。「弾けません」の一言で終わってもいいのですが、栩谷がギターを弾けるということに違和感はなかったんです。栩谷は情報が少ない人物だからこそムードがある方なので、直感で弾くことを選択しました」

荒井監督:「でも、あれは計算外だったからなぁ。別のシーンでも綾野が歌うシーンがあったから、綾野が歌ってばっかりになってしまうと思ってカットしたんだよね(笑)」
脚本の完成度をより高めた
ピンク映画への“レクイエム”

– 脚本を読んだときはいかがでしたか?
綾野さん:「 映画人の匂いが沸き立つ“脚本”に出会いました。圧倒的な完成度の高さで、読み物として完成されている強度がありました。これを映像化する上でこの完成度をどこまで追求できるのか、という畏怖と緊張感がありました。芝居はすべて、最終的に現場に委ねられるので、撮影前に荒井さんに“栩谷は、どう生きればいいですか?と尋ねたとき、“脚本なんてただの書き物だから、自由にやればいいんだよ”と仰ったんです。その潔さを目の当たりにしたとき、“栩谷が目の前にいる”と思いました。そのときからずっと荒井さんを観察しながら、栩谷を丁寧に形成していきました」

– 今作では「ピンク映画」のオマージュも強く感じました。
荒井監督:「僕自身、ピンク映画出身でね。10年くらい前からピンク映画を撮影できる機会や上映できる映画館が減っていったり、震災が重なったり、民主党から自民党に変わったり、日本が変わっていく気配を感じていた。その変化に、ピンク映画が無くなっていく喪失感を重ねて、“ピンク映画へのレクイエム”というのをやってみたいなと思ったんだよね。喪失に対する気持ちを一番表現できる大きな存在は、“死んでしまった人”。だからこそ、祥子が死んでいるシーンから始まった。“脚本は直せるけど、人生は直せない”って、思っていて、だからこそ、僕は映画を作っているんだと思う。“あのとき、ああすれば良かった”という後悔、人生で出来なかったことを映画と脚本でやっているのかもしれない」

綾野さん:「僕が感じた、“これぞ脚本”の意味が、今結実した気がします。完成されていたというのは、ある種のレクイエムだったのだと。完成された脚本を下から撮影という“炎”をあてて、もう一度あぶり出さないといけない。煙になっていくのは残酷ですがあぶり出された匂いはちゃんと残ります。今作はそういう映画に仕上がったと確信しています」
エンドロールで見届けたい
栩谷の長い“男の言い訳”

– 栩谷と伊関の絶妙な距離感も印象的でした。伊関役の柄本佑さんと事前に打ち合わせなどしたのでしょうか?
綾野さん:「していないです。テスト撮影の段階で、脚本に書かれている台詞を、感情をのせて吐露するように出して、現場でチューニングしながら撮影を進めていきます。何を喋るかは脚本上決まっていますが、その役をどう“生きるのか”は、撮影がスタートしてから自然とお互いチューニングしあっているという感じです。そういう芝居に対しての向き合い方は、佑くんと祥子役のほなみさん(さとうほなみ)と近い感覚でいられ、親和性がありました。昔からやっていたかのようなムードで、自然と役に入っていくことができました。」
– お二人の役者としての印象はいかがでしたか?
綾野さん:「佑くんの事が個人的にファンでして。魅力的な方で、声も芳醇。ずっとうっとりしていました。 ほなみさんは、エンジンの大きい方。すごく直感的ですが、地に足がついている。シンプルにいうと、カッコいい方です」
– 劇中では雨のシーンも多かったですね。
荒井監督:「映像で見るとカラーで綺麗に見えるけど、現場は大変だったよね(笑)。新宿のゴールデン街で撮影した雨のシーンは、終電で集合して、午前3時頃から撮影をはじめました。やっと撮影がスタートしたのはいいけど、カメラに雫は垂れてくるし、綾野はずぶ濡れで転がらなきゃいけないし……(笑)」
綾野さん:「朝まで撮影して、そのまま別の場所に移動して昼前まで撮影していましたよね」
荒井監督:「それが、2日目か3日目の話。これは、これからどうなるんだろうと思ったよ(笑)」
綾野さん:「(笑)。雨のシーンに関しては、栩谷を演じる上では非常に重要な要素だったと思います。一見、雨は弊害に思えますが、冷たい雨が体に染みこんでいくことで体温を調整していくと、生きているという実感に繋がっていく。そして、雨降らしチームの技術が本当に素晴らしいんです。カメラの前や役者に当たっている部分だけでなく、50m以上先の背景まで雨が降っている演出をしていて感動しました」

– 祥子がカラオケで歌うシーンなどで登場する、山口百恵さんの名曲「さよならの向う側」も物語により一層深みを与えているように思いました。
綾野さん:「実は脚本の最後のページは、「さよならの向う側」の歌詞で締めくくられているんです。栩谷が祥子と歌うシーンは、現場で荒井さんが“歌える?”と仰って撮影しました」
荒井監督:「あのシーンは色んな場所に分けて使わせてもらいました。だって、あの曲、6分くらいあって長いんです(笑)さすがに1つのシーンで丸ごと使うことはできないからね。だけど、分けて使いたいくらい、栩谷と祥子の表情と雰囲気が本当に良かったシーンなんだよね」
綾野さん:「そうですね。栩谷って無愛想だし、サービス精神がない人。ですが、そんな彼が“実は思っていた感情”が表れているシーン。この、“実は”という部分が、栩谷っぽいと思いました。栩谷と祥子の物語を表現する上で、とても大切なシーンになりました。そしてカラーだからこそ、残酷で美しい眩しさもある。この歌を通して、そんな“男の長い言い訳”に辿り着けるのではないかと思います」

荒井監督と綾野さんの和やかな掛け合いも印象的だったインタビュー。荒井監督の答えに綾野さんも“僕も聞いてみたかったんです”とインタビュアーと一緒に真剣に聞き入るシーンもあったり、時には綾野さんの荒井監督に対するユニークなツッコミで場が和んだり、今作の撮影現場で培ってきたお互いの信頼と絆が垣間見えた時間でもありました。

荒井監督による斬新な演出と、その役を“生きる”ことを徹底した綾野さんの演技に対する想いが、登場人物に命を吹き込み、彼らが生きてきた世界に浸れるような感覚になれる映画でした。
映画「花腐し」は伏見ミリオン座ほかにて、11月10日(金)より公開です。