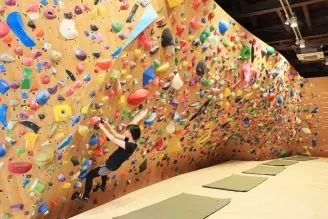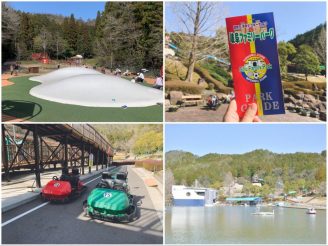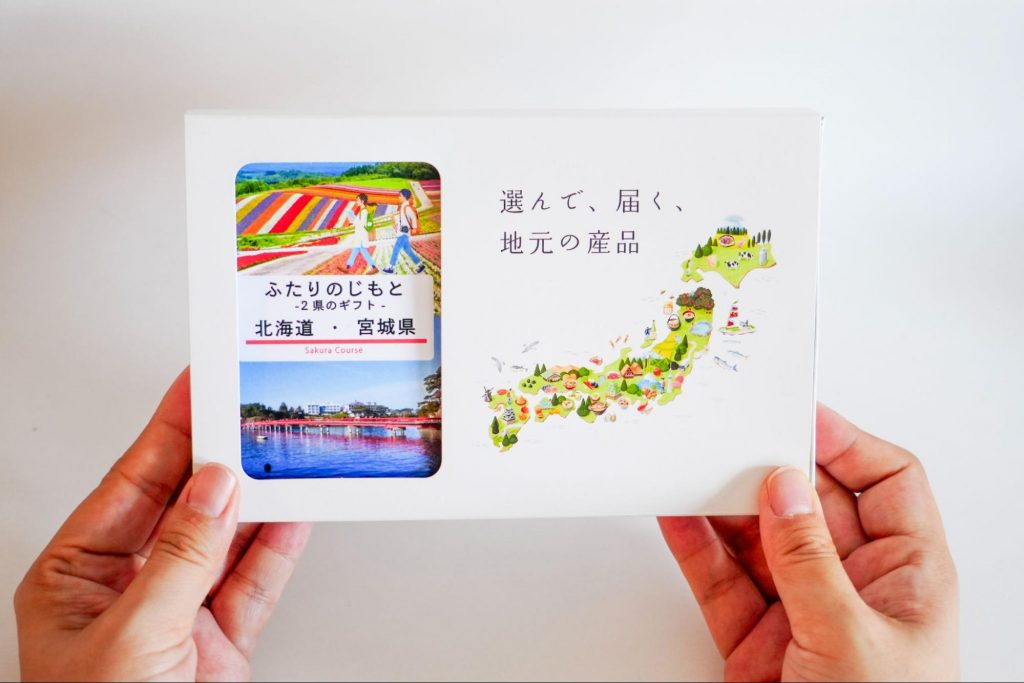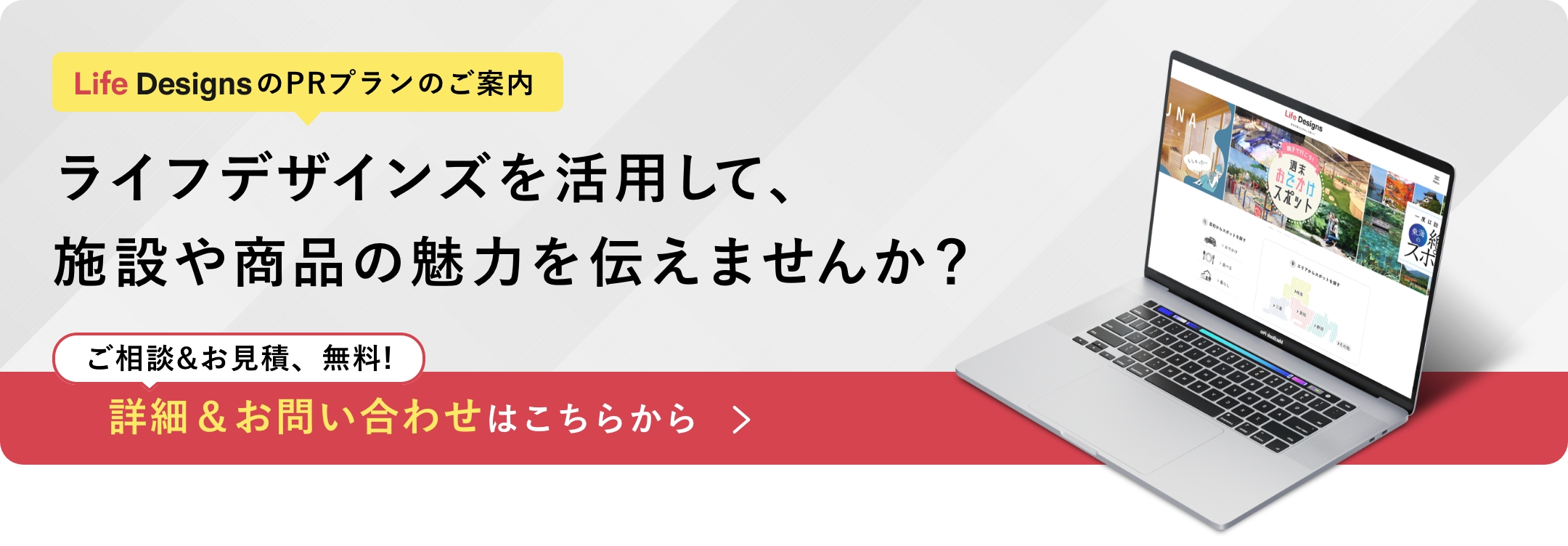目次
名古屋城から徳川園に至るエリアは、文化人・財界人の屋敷が連なり「文化のみち」と名付けられています。 江戸時代から明治、大正へと続く名古屋の近代化を担った文化人たちが暮らした歴史的建造物が多く残されています。
その中でも、ひときわ目をひくのが「文化のみち二葉館(旧川上貞奴邸)」です。オレンジ色の洋風屋根、ステンドガラスや螺旋階段など、大正ロマンの香り漂うこの館のみどころをたっぷりとご紹介していきます。
「文化のみち二葉館」とは?

「日本初の女優」と謳われた川上貞奴(1871〜1946年)。「日本の電力王」といわれた福沢諭吉の娘婿にあたる福沢桃介(1868〜1938年)。旧知の仲だった二人は事業のパートナーとして、大正から昭和にかけてこの館でともに暮らしていました。もともとは東区東二葉町にありましたが、現在の場所に移築復元され「文化のみち二葉館」として2005年に開館しました。
2,000坪を超える敷地に建てられた和洋折衷の斬新で豪華な建物は「二葉御殿」と呼ばれ、政治家や財界人、文化人が訪れるサロンとなりました。設計を担当したのは、当時新進気鋭の住宅会社として知られていた「あめりか屋」。電力王と呼ばれた桃介は東海地方に数々の水力発電所を築き、当時としては驚くほどの電気装備が施されたこの邸宅で、貞奴とともに電気のある暮らしを多くの人々へアピールしたといわれています。また、貞奴の好みも至る所に取り入れられました。

場所は、桜通線「高岳」駅から徒歩10分ほど。

国の「登録有形文化財」、名古屋市の「景観重要建造物」に指定されています。

ではさっそく大正ロマンの世界へ行ってみましょう。
名古屋のセレブが集った「大広間」


玄関入ってすぐのところにある大広間は、財界人や文化人たちが集まるサロンとして機能していました。当時、名古屋で「川上絹布」という製造工場の女社長だった川上貞奴。木曽川の電源開発に取り組み「電力王」と呼ばれていた福沢桃介。まさに名古屋のセレブ代表とも言える二人は、当時の財界人や文化人たちを招待し、贅を尽くしたこの部屋でもてなしていたようです。
大広間のみどころ①「ステンドグラス」
 大広間西側にあるステンドグラス「初夏」
大広間西側にあるステンドグラス「初夏」
 大広間西側にあるステンドグラス「踊り子」
大広間西側にあるステンドグラス「踊り子」
大広間のみどころの1つ目は「ステンドグラス」。
二葉館内のステンドグラスは、当時の有名なデザイナーであり福沢桃介の義弟・杉浦非水の原画をもとに作成したものです。杉浦非水は、東京美術学校(現東京芸術大学)出身で多摩帝国美術学校(現多摩美術大学)の校長を務め、日本のグラフィックデザインの先駆者といわれるほどの人物。二葉館に行かれた際には、ぜひステンドグラスのデザインにも注目してみてくださいね。


大広間に隣接する展示室(旧食堂)にも美しいステンドグラスが。こちらは、槍ヶ岳などの山をあらわした「アルプス」と題されたものです。
大広間のみどころ②「創設当時のソファ」

 ソファの張り地。ぜひ実際に座り心地を体感してみてくださいね。
ソファの張り地。ぜひ実際に座り心地を体感してみてくださいね。
大広間のみどころの2つ目は、「大広間の一角にあるソファ」。
こちらは、改築時、別の部屋に転用されていたソファを、一度解体した上で、当時の材料や工法をもとに復元したもの。木組みやスプリングは当時のものを再利用しています。創設当時のものとは、思えない座り心地にとても驚きました。
大広間のみどころ③「木製の螺旋階段」


そして大広間の中で最も目を引くのが、2階へと続く螺旋階段。美しい曲線を描く木製の階段は、裏側にまで板が貼られているのが特徴です。赤い絨毯が敷かれ、電気の力で明るく照らされた舞台のセットのような階段は圧巻。細部にまでていねいに装飾がほどこされています。


川上貞奴の当時の暮らしが再現された和室

ここでもう少し川上貞奴について詳しくご紹介していきます。
NHKの大河ドラマにもなった川上貞奴(本名:小山貞)は、幼い頃に芸者置屋の養女となり、その後売れっ子芸者になり「奴」とよばれるように。福沢桃介に出会ったのもこの頃のことです。
その後、明治27年(1894)に「オッペケペー節」で有名な川上音二郎と結婚。川上一座が興行のため渡ったアメリカ・サンフランシスコの公演で、女優「貞奴」として初めて舞台に上がり、アメリカ各地で評価を得ます。パリ万博で公演し、フランス政府から勲章を授かるなど、「マダム貞奴」として世界に知られる女優となりました。


大広間と食堂の奥は、そんな川上貞奴が暮らしていた「旧婦人室」です。和室は建設当時のままで、この部分は国の文化財として登録されています。調度品や家具などで室内が再現され、貞奴の当時の暮らしを垣間見ることができます。貞奴愛用の着物や帯も季節に合わせて展示されています。

「日本の電力王」と呼ばれ、木曽川水系の発電事業を進めていた福沢桃介は、二葉館を当時最先端の電化住宅にし、室内や廊下の照明にもこだわりました。館内には大理石でできた配電場や、貞奴がどこにいても女中さんを呼ぶことのできた電気式のベルなど、当時の最先端の電化装置が設置されています。
また、電灯のスイッチも当時使用されていたものが残っています。ONとOFFのボタンが上下に並んいるデザインは、現在ではなかなかみられないですよね。